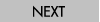平安末期から鎌倉の初期にかけて、寺社仏閣に仏像を刻んだ仏師は星の数ほど存在した。けれども、日本の仏像彫刻の道を登りつめ最高峰に到達し、その後、仏像彫刻としては日本文化史上、この人を超える仏師は遂に現れなかった。その人こそ運慶だ。
運慶という仏師は、その生涯の多くが謎に包まれている。六波羅蜜寺に現存する「運慶の像」と称される木像僧形の座像がある。これを見ると、やや尖った頭頂に頑丈な体躯、数珠を指に絡ませ、「法眼」の位を許された僧侶だが、漂う朴訥な風情は、一介の職人だ。運慶に限らず、当時の仏師は例外なく、寺院に付属する職人集団であり、彼も南都=奈良を本拠とする、東大寺や興福寺に所属し仏像の製作・補修にあたる一団の一人に過ぎなかった。したがって、仏師運慶も、決して現代的な意味での芸術家ではなかった。
運慶は1140年代から1150年代の初めにかけて生まれたと考えられる。平等院鳳凰堂に代表される浄土信仰が一世を風靡し、貴族と結びついた京都仏師たちは、優雅な阿弥陀如来像を次々と生み出していく。その京都仏師の頂点にあったのが定朝であり、運慶が生まれた頃には定朝直系の仏師が、仏像彫刻の主流となっていた。中でも院尊を棟梁とする院派、明円を頭と仰ぐ円派の二代派閥が、都でその創造の優秀さを競い合っていた。運慶はこうした京都仏師を横目に、創造の機会すらほとんどない、修復をもっぱらとする旧勢力の南都=奈良仏師の集団に、父の康慶の代から参加していたのだ。康慶は奈良仏師でも傍流の出であり、運慶には仏像の修理の末端しか回ってこなかったようだ。
こうした劣勢な環境の中で、わずかでも幸運だったのは興福寺が権門・藤原氏の氏寺だったことだ。鎌倉時代までの日本政治史は、いわば藤原一族の歴史であり、権力と富はこの一門のみに集まった。そうした家を大檀那としている限り、「食うに困らぬ」の思いであったろう。保元の乱(1156)、平治の乱(1159)を経て、藤原氏の権勢が地に落ちて、恐らく仏像の修理もこれまでのようには行われなくなったはずだ。
だが、それから間もなくして興福寺の系列の忍辱山円成寺の大日如来像を造顕する仕事が入った。どういう経緯からか不明だが、安元元年(1175)から1年をかけ、運慶は父とともに仏像制作に参加している。台座に「大仏師康慶実弟子運慶」と記されており、この仕事が運慶の名を史上、確実に登場させることになった。ただ、この像は後の運慶の荒々しい写実性のある作品に比べると、際立って王朝風の優雅さに彩られ端正で清冽ではあるが、独創的とは言い難く、いかにも優等生の作品といった印象が強い。この時代、政治は明らかに貴族の手から武士の手へ、平家そして源氏隆盛となり、興福寺でも多くの伽藍が消失。奈良時代の数多の仏像が焼き尽くされる。と同時に、運慶の姿は忽然と歴史の舞台から消える。
運慶が再び現れるのは南都最大の寺院、東大寺の復興においてのことになる。建久6年(1195)、大仏の開眼供養に際し、運慶は「法眼」に叙せられていた。翌建久7年、東大寺大仏殿で虚空蔵菩薩像、時国天像を運慶が製作。ただ、これらは現存していない。運慶の作風が後世に伝えられるのは建仁3年(1203)の作品まで待たねばならない。弟子の快慶とともに、20年に及ぶ東大寺再建事業の最後を飾って、東大寺南大門に安置する阿吽二体の金剛力士像=仁王像を彫り上げたのだ。仁王の筋骨の逞しさ、人間くさい勇壮さ、迫力・切れ味ともに、この作品は戦乱の中から生まれたことを雄弁に語っている。こうして運慶は、仏像彫刻界の頂点に立った。
金剛力士像が完成した5年後、承元2年(1208)、興福寺の北円堂で中尊の弥勒像をはじめ、脇侍二体、四天王、羅漢二体(無著・世親)が造られた。現存する弥勒と羅漢二体は、運慶を日本彫刻史上にその名を刻ませた最高の傑作といえるだろう。
(参考資料)加来耕三「日本創始者列伝」