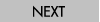新井白石は江戸中期、六代将軍徳川家宣、七代将軍徳川家継に仕え、幕政改革の理想に燃えた、“鬼”の異名を取った稀代の学者政治家だ。その学識の高さは、その当時における、というより江戸時代を通じてすら、比較すべき者の少ない学者だった。
白石が儒者として俸禄四十人扶持(年72石)で甲府藩に召抱えられたのは元禄6年。彼が37歳の時だ。そして、それ以前の白石は久留里藩の土屋家、古河藩の堀田家と2度も浪人し、20歳代から長い間貧しい生活を強いられ、37歳のその時は本所で私塾を開いていた。この間、白石の器量を見込んでか、富裕な商家から二つも縁談があった。その一つは相手が河村瑞賢の孫娘だったので、承知すれば豪商の家の婿に納まることもできたわけだったが、白石は断った。甲府藩に仕えることができたのは、学問の師である木下順庵の推挙によるものだった。
元禄15年12年に200俵20人扶持に引き上げられた。加増の理由はこの年3月、起草してからほぼ1年余を経て完成、藩主・網豊に献じた『藩翰譜』の成功に対する褒賞ではないかと思われた。藩翰譜は、儒者というよりは歴史家としての白石の本領を示した労作で、12巻18冊、ほかに凡例総目次1巻を加えた大著だった。ここに書きとめられた諸家の数は333家におよび、これを記すのに紙1480枚を費やしたが、草稿、浄写の作業に写し損じを加えれば費やした紙数は3000枚に上ったろう。いずれにしても、ようやく白石は貧しさを気にしなくて済む身分になった。
五代将軍綱吉の死後、白石は側用人・間部詮房とともに、六代将軍家宣となった藩主の天下の治世に乗り出していく。「勘解由(白石)を経書を講ずるだけの儒者とは思っておらぬ。政を助けよ。意見があれば、憚りなく申せ」という将軍家宣の篤い信頼のもとに、白石は「政治顧問」的な立場で様々な下問に対し、先代までの慣例や事績にこだわらない、あるべき意見も含め献策する。「生類憐れみの令」の停止およびその大赦考、改鋳通貨「宝永通宝」の通用停止、武家諸法度新令句解などがそうだ。こうした出仕が評価され、白石は200石加増され、従来の200俵20人扶持を300石に直し、計500石とされた。
白石は宝永6年(1709)11月、江戸小石川茗荷谷の通称切支丹屋敷で、ヨーロッパの学問16科を修めたというイタリア人、ジョバンニ・バチスタ・シドッチと会い、尋問する。シドッチは薩摩・屋久島に流れ着いた宣教師だ。白石はこの尋問の前に、あらかじめカトリックの教義について予備知識を得たいと思い数冊の書物を読んだ。
白石が西洋人に接したのは初めてであり、最初シドッチが何を言っているのか分からなかったが、次第に分かってきた。他の日本人には全く分からなかったが、白石はシドッチの日本語に近畿地方や山陰、九州の方言が入り混じっていることに気付いた。発音にもシドッチのクセが出る。そのクセは当然、一定の法則性のようなものがある。それを白石は見抜いた。これらに照らして理解していけば、シドッチの日本語が自然と分かってくるのだ。白石の頭脳が、シドッチの不思議な日本語を理解させたのだ。白石はシドッチの持っている知識を貪婪に吸収した。白石はこれを『西洋紀聞』に書いたが、シドッチの母国語までは理解するには至らなかった。イタリア語を吸収できるほどの時間的余裕がなかったからだ。しかし、白石が行った尋問で、結果として彼自身の学識の高さを示すことになったことは確かだ。1.貨幣の改鋳の停止
2.裁判の公正 3.長崎貿易の見直し−など白石の献策は、それまでの幕府官僚の施策とは明らかに異なり、本質的には的を射たものだった。が、白石はやはり学者で潔癖でありすぎた。そのため“鬼”の異名と取ることになり、周囲に煙たがられた。そして、彼の得意時代はそれほど長くは続かなかった。正徳2年、10月14日、家宣が享年51歳で亡くなり、嫡子鍋松(家継)がわずか4歳で将軍職を継いだが、家継も8歳で亡くなってしまったのだ。結局、白石が幕政にタッチしたのは7年ほどで、紀州藩から入った八代将軍吉宗が登場すると、即、更迭され、彼の「善政」はすべてご破算になってしまう。
ただ、白石はこれからが凡人とは違った。60歳から死ぬまでの9年間、『折りたく柴の記』をはじめ数々の名著を執筆するのだ。彼が政治家として得意の時代を続けていたら、これらの名著は生まれなかったかも知れない。
(参考資料)藤沢周平「市塵」、司馬遼太郎「歴史の中の日本− 白石と松陰の場合」、永井路子「にっぽん亭主五十人史」